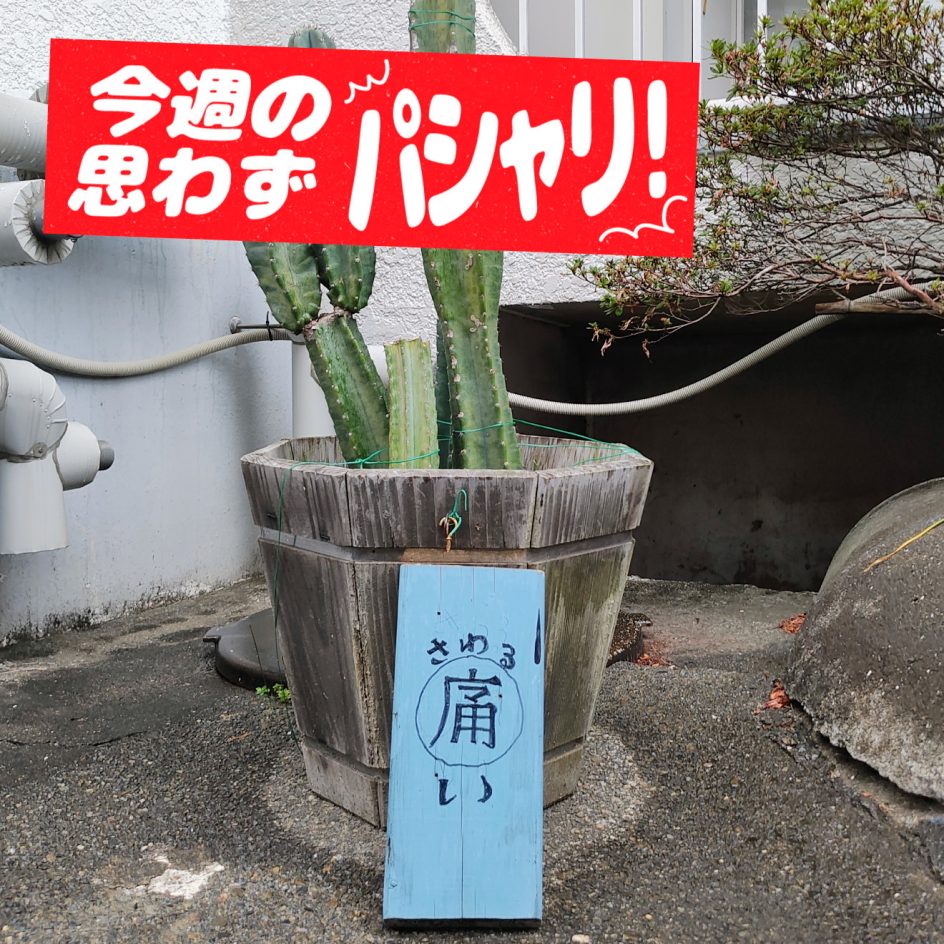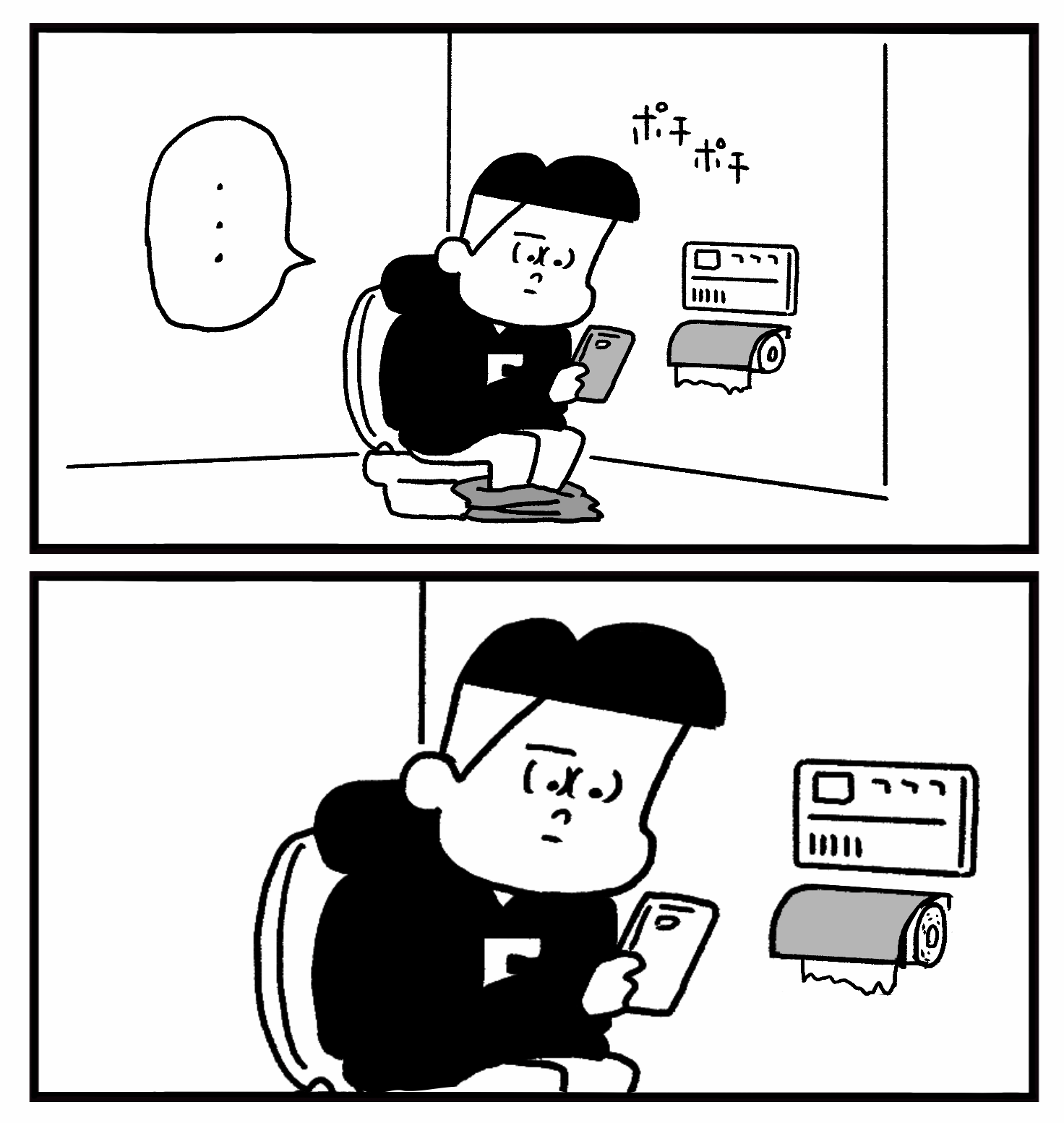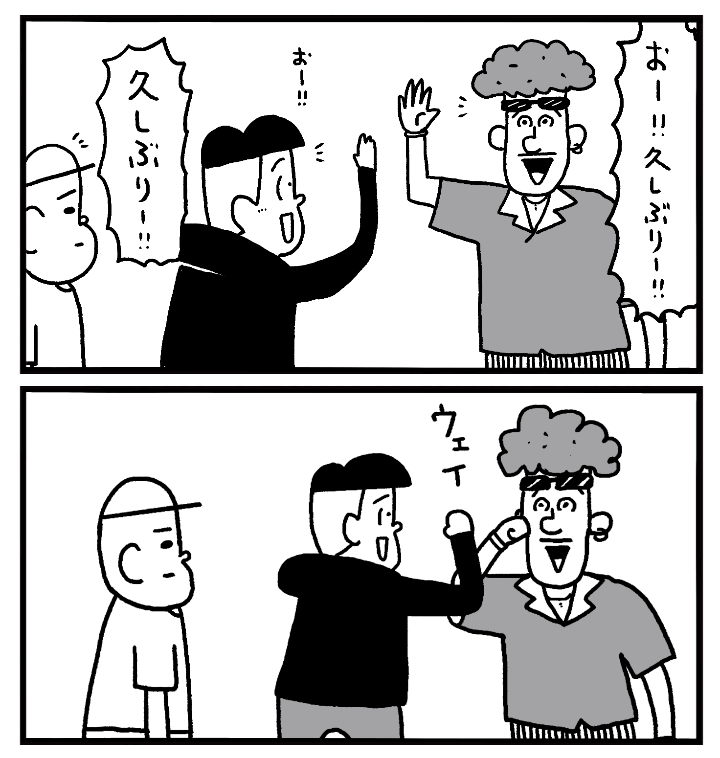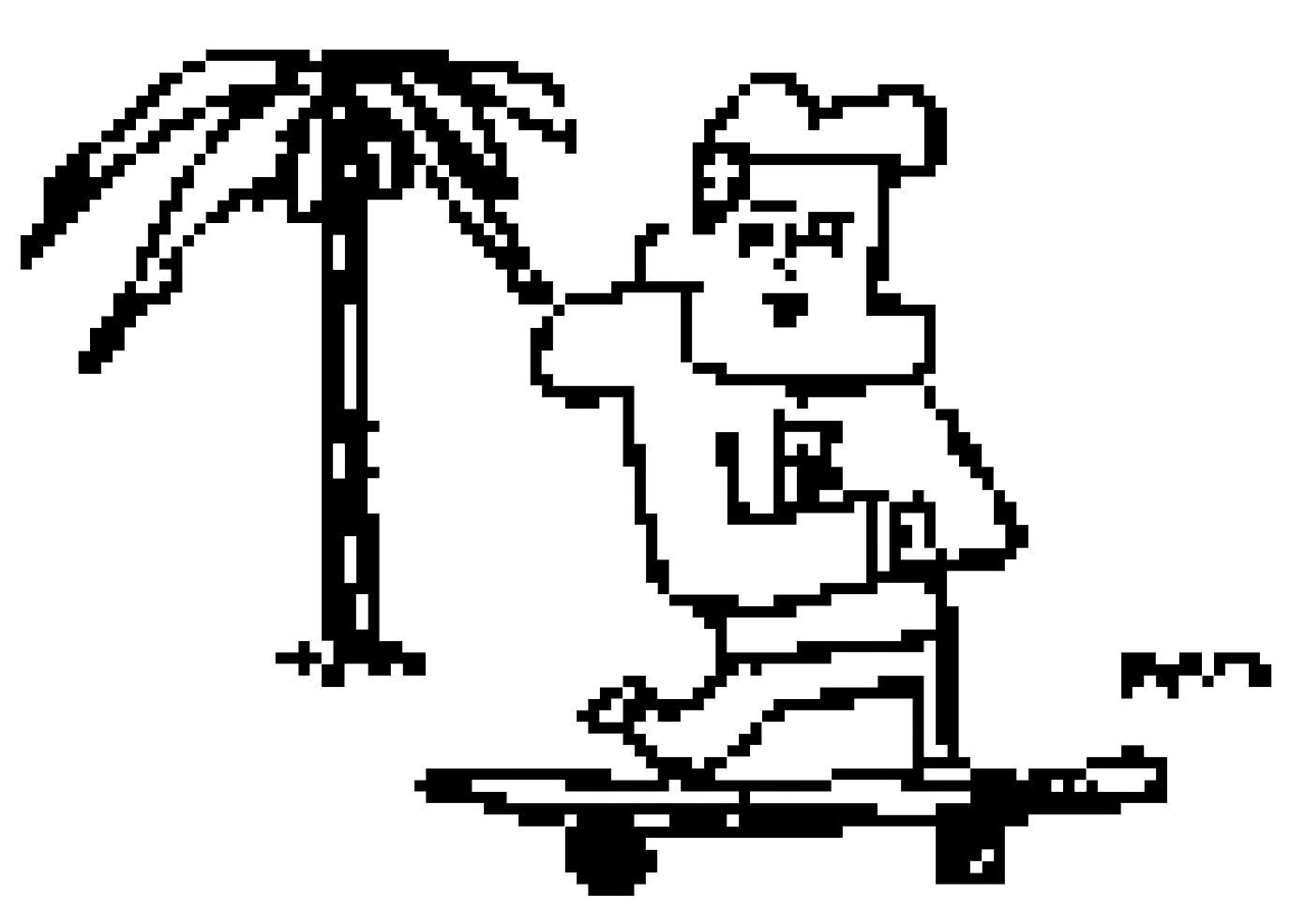サブスクが主流になり、外でも家でも大量のコンテンツを消費できる時代だからこそ、何を観たらいいのか分からない!という人も多いのでは?「シネマフリーク!!」では、映画館で上映中の話題作から、ちょっとニッチなミニシアター作品、おうちで観ることのできる配信作品など数多ある映像作品の中からライターの独断と偏見で、いま観てほしい一本を深掘りします。
今回は是枝裕和 × 坂元裕二 × 坂本龍一という国内最高峰の才能が集結した話題作『怪物』をご紹介。先日閉幕したカンヌ国際映画祭では、脚本賞とLGBTQやクィアを題材に扱った作品に贈られるクィア・パルム賞を受賞し、国内外から高い注目を集めている作品です。

タイトル:『怪物』
監督・編集:是枝裕和
脚本:坂元裕二
音楽:坂本龍一
出演:安藤サクラ、永山瑛太、黒川想矢、柊木陽太 / 高畑充希、角田晃広、中村獅童 / 田中裕子
配給:東宝、ギャガ
2023年製作/125分/日本
6月2日(金)全国ロードショー
<あらすじ>
大きな湖のある郊外の町。息子を愛するシングルマザー、生徒思いの学校教師、そして無邪気な子どもたちが平穏な日常を送っている。そんなある日、学校でケンカが起きる。それはよくある子ども同士のケンカのように見えたが、当人たちの主張は食い違い、それが次第に社会やメディアをも巻き込んだ大事へと発展していく。そしてある嵐の朝、子どもたちがこつ然と姿を消してしまう ——
物語の構造上できる限り前情報を入れずに、繰り返し観ていくことで新たな発見が生まれる本作。なるべく多くの方にその魅力を体感してもらうべく、今回はなるべくネタバレをせずに作品の輪郭からなぞっていきたいと思います。
映画を中心にコンスタントに作品を作り続け、国内外から注目を浴びる是枝監督と長年テレビドラマを中心に良質な物語を送り届けてきた坂元裕二、そして惜しくも今年の3月に息を引き取るまで音楽と自らの言葉を通して環境や社会の問題にスポットを当て続けてきた坂本龍一という日本の至宝とも言うべき作家が集結し、まるでラブレターのように、互いの仕事やキャリアに対しての敬意がこもった三人のコメントとともに発表された本作。
テレビマンとしてドキュメンタリーの演出からキャリアをスタートした是枝監督は、『誰も知らない』(2004)や『万引き家族』(2018)など、福祉や社会の実情に向き合って脚本から映画を作っていくことでも知られていますが、坂元裕二という異なる視点の才能とタッグを組んだ時にどのように物語が編まれていくのか。いちファンとして、想像がなかなかできませんでした。

坂元裕二と言えば、90年代には「東京ラブストーリー」で一世を風靡し、2000年代以降も「最高の離婚」、「カルテット」、「大豆田とわ子と三人の元夫」など、くせになるキャラクター設計と独特な会話劇で、テレビ離れが進む令和においてもドラマ文化を進化させ続けてきた日本を代表するストーリーテラー。コメディタッチで描かれる人間ドラマの印象が強いという人も多いかもしれませんが、「それでも、生きてゆく」や「Mother」など、社会問題をテーマにした作品も多く、改めてキャリアを振り返ると是枝監督の視点と共鳴する部分はこれまでも多く描かれてきたような気がします。
実際に本作でも、小学五年生の新学期の季節に起こる大小さまざまな事件をベースに、虚言や同調圧力から生まれる炎上やモンスターペアレント、DVなど現代におけるさまざまな社会問題がキーワードとして散りばめられています。子供を守るために教師や学校を問い詰める母親、なにやら納得のいかない教師。タイトルとなっている“怪物”はいったいなんのことで、誰を指しているのか?モノローグは一切なく、目の前で繰り広げられる出来事と発せられる言葉一つひとつを拾い集めて、全体像を把握できたところで、また異なる視点によって再度振り返ってゆく。そのうちに一連の事実に対して、人の数だけ存在する複数の真実が浮かび上がってきます。

『万引き家族』以来二度目の是枝組参加となるアカデミー賞女優・安藤サクラが愛情あふれる主人公を演じる一方で、坂元作品の常連でもある永山瑛太や高畑充希、田中裕子といった役者たちがどこか訳あり顔で不穏な空気を作り出し、不協和音のようなストーリーが構築されていきます。そして、黒川想矢、柊木陽太という才能あふれる子役たちによる、思春期特有の眩しくも繊細な心の機微にフォーカスが当たるにつれて、まったく異なるテーマが少しずつ見えてきます。
このまま感想をもっと語りたいのですが、語り出したら止まらずにネタバレ王として炎上してしまいそうなので止めておきます(笑)。よく映画の煽り文句として衝撃のラストというワードがありますが、個人的にこの作品でも終盤からエンドロールにかけてサ活の「ととのう」に近しい感情が沸き起こるシーンがありました。その瞬間に、劇伴として携わった坂本龍一も含めて文字通り奇跡のアンサンブルとなった本作の “怪物” 度が一層鮮明に浮かび上がるはず。ぜひ、ピュアな気持ちで怪物探しを楽しんでみてください。