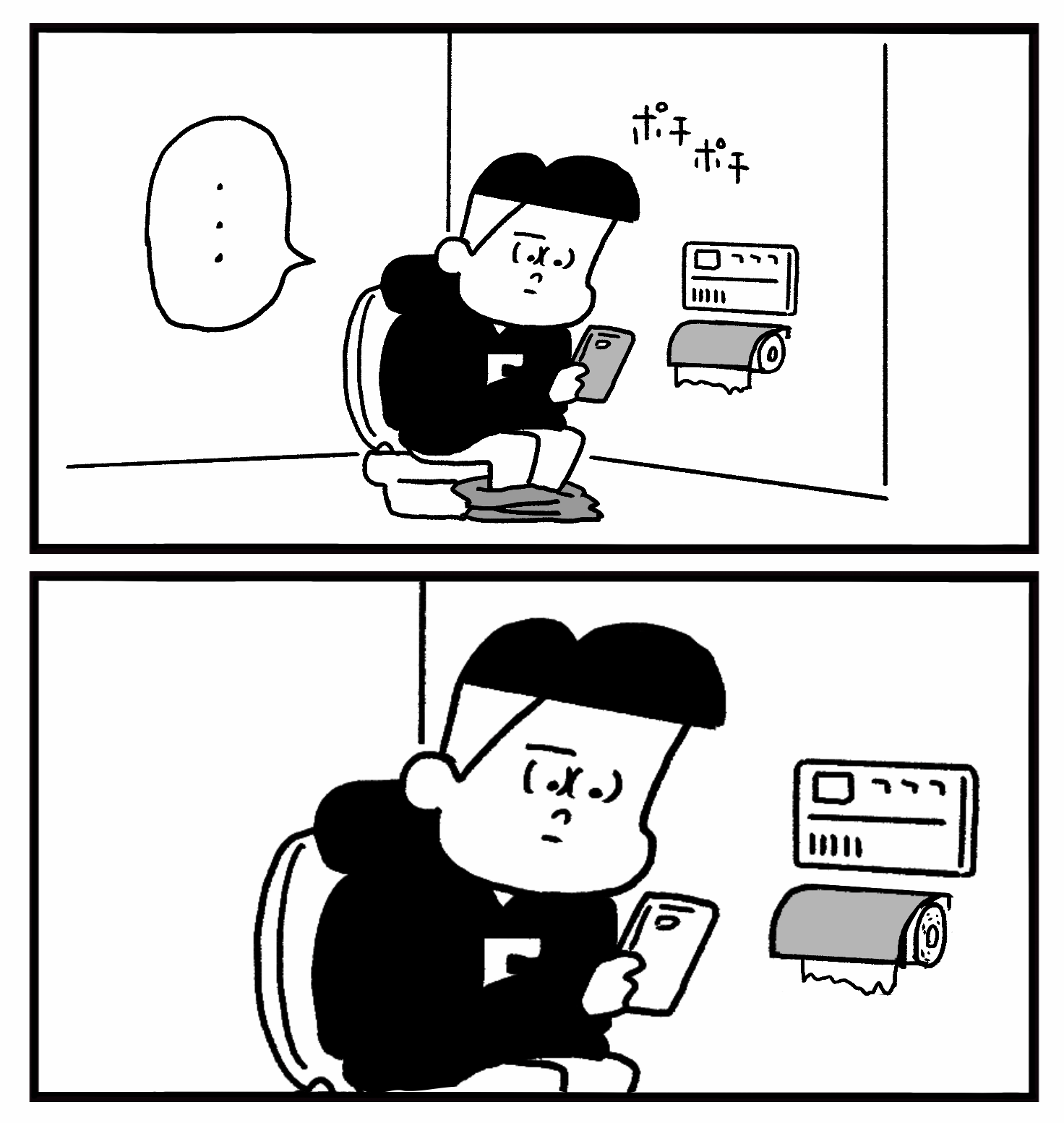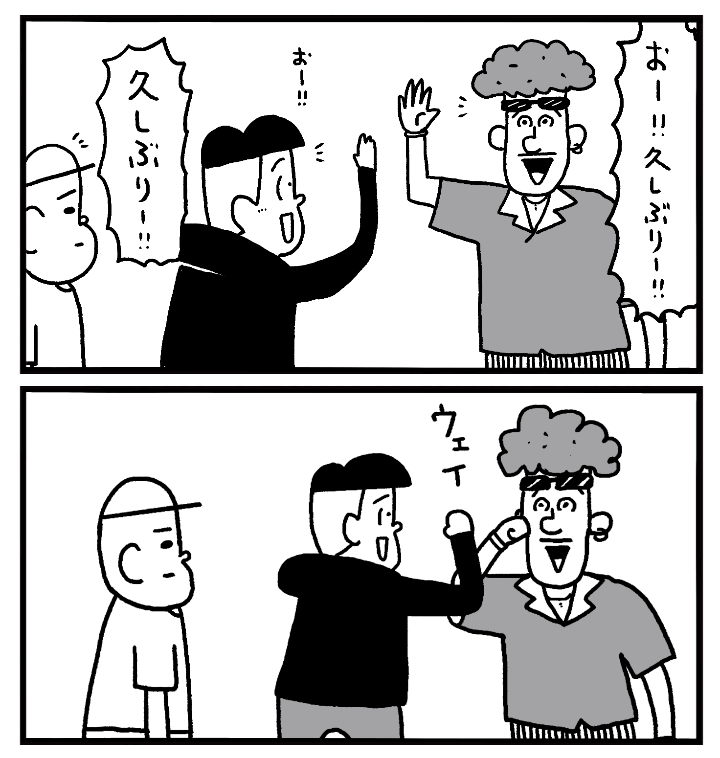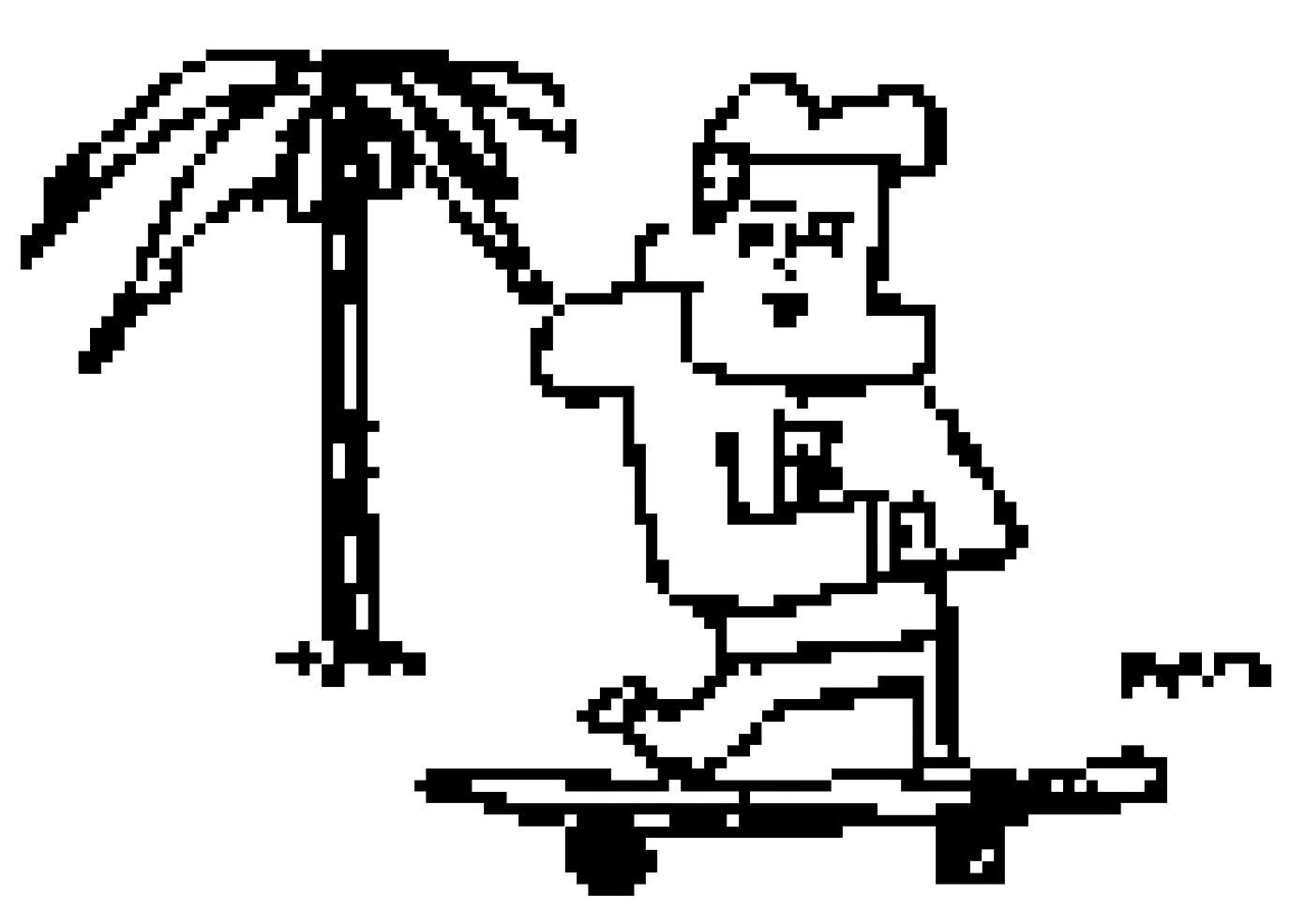“Culture Freak(カルチャー・フリーク)”。それは、アートや身体表現、ゲームや音楽、「〜道」など、さまざまなカルチャーに精通する人たち。時に熱狂的なまでに、その “道” を極めようと努める、“フリーク” な人々のこと。
本シリーズ連載では、そんな “Culture Freak” たちが心に抱く熱い想いや哲学を、インタビュー形式でお届け。記念すべき第一回目に登場するのは、2023年6月に、BiSHのメンバー・リンリンとしての活動を終え、アート活動を始めたMISATO ANDO氏。
「曲」としての形をもったアートから、「イラスト・ファッション・立体作品」としての、新たな “形” を求道する彼女。インタビューを通じて、常に等身大であり続ける彼女の思想や哲学を深堀りしていく。彼女が見据える新たなアートの形と、そのフリーク(熱狂的)なまでの姿勢・視線を紐解いていく。

時は、2023年10月4日。雨が降りしきる夜、とある展覧会会場にて、とあるインタビューが行なわれた。「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023 “Time to Change”」と題されたその展覧会は、『アートを軸に、音楽・食・ファッション・ライフスタイルなどの隣接したカルチャーを一堂に会することで、領域を超えてそれぞれのカルチャーの魅力に気付きを生み出すとともに、アートに対する新しい出会いや発見を設計することを目指す、領域横断型のアートフェスティバル』だという。
そんな展覧会の会場に、一人の “芸術家” が参加すると聞き、駆けつけた。彼女の名は、MISATO ANDO。国内外問わず熱狂的なファン(清掃員)を持つ “楽器を持たないパンクバンド”・BiSHの “無口担当” として、名を「リンリン」と定めて活動してきた彼女は、今、筆を持ち、美術としての新たな “武器” を手にし、一人の “芸術家” としてのスタートラインに立つ。
ーーリンリンさん、改め、MISATO ANDOさん。今日はよろしくお願いします。

MISATO ANDO(以下:ANDO):よろしくお願いします。
ーー音楽を芸術として扱うミュージシャンから、一人の美術家へ。その転身を行なうにあたって、どのような想いがあったのでしょうか?
ANDO:BiSHが解散する2,3年前、私は、もしも解散するならば、一人で音楽をやっていこうと思っていたんです。アイナ・ジ・エンドだったり、アユニ・Dだったりのソロ活動が始まって、定着してきていた時期だったのも、正直少々あって。音楽のソフトを使い、なんとなく準備をしておこう、って。ただ、それよりもひとつ、大きな契機があったんです。
ーー大きな契機、ですか。

ANDO:山梨県にある、キース・ヘリング美術館を訪れてみたんです。友人とともに。その頃は、アートに関する知識など一切なく、キース・ヘリングについてはなんとなく知っているぐらいのテンションでした。とあるファストファッションのブランドがTシャツを手がけているよな、ぐらいでしたね。そんなイメージしか持たないまま、キース・ヘリング美術館を訪れました。
ーーそれが、ひとつの契機になったのでしょうか?

ANDO:とにかく、ものすごい衝撃を受けたんです。ひとつ目の部屋、とても暗い部屋に入った際、とある文字列が見えて。キース・ヘリングが残したメッセージでした。『アートというものは、人間よりも長生きで、いつまでも残り続けるものだ』という意味の言葉。『Art is for everybody. (芸術はみんなのためのものだ)』と。わたし自身、知識として、遠い昔に彼が亡くなってしまっていることは知っていました。ただ、その文字列を目にした瞬間に、思ったんですよね。「わたしでも何かになれるんじゃないか」と。
ーーキース・ヘリングの言葉に出会えたことが、ひとつのきっかけになった。

ANDO:言葉だけでなく、もちろん、作品にもすごく影響されたように思います。たとえばキース・ヘリングがよく題材として描く赤ちゃんのペイントには、人間のもっとも無垢な姿を見せたいという欲求・願望があった。彼の作品を見ていくうちに、説明キャプションの文章を読まなくても、彼の描くものたちの “理由” がわかっていったんです。自分なりに解釈をすることができるようになっていった。いわば「意気投合」というか。作品だけが生きていて、作者は亡くなってしまったけれど、あの場所でキース・ヘリングとわたしは繋がっていたんだ、と思うんですよね。芸術作品を通じてそういう体験を得られたのは、それが初めてのことでした。なんだか、救われたような気がしたんですよ。
ーー救われたような気がした。なるほど。

ANDO:「わたし、絵をやってみようかな」と思えたんです。彼の作品たちを目にして。もともと図工の授業や落書きなんかは好きだったのですが、絵を描くこと自体は「別に……」といった感じでしたが、本当、キース・ヘリングに出会ってから、まっさらな心で「絵を描いてみよう」と思ったんですよね。彼は、AIDSで命を落としてしまったのですが、死を確信した直前に、鉛筆も上手く握れなくなってしまったにも関わらず、赤ちゃんの絵を描いたらしいんですよ。それが、きっと今みんなの頭に浮かんでいる、あの絵なんだそうです。
彼の絵には、優しさとか、人間らしさとか、本当にいろんなものが詰まっているんです。魂が、わかりやすい形で、詰め込まれている。そんな作品たちを見て、わたしもきっと、“作品” として、自分のことをたくさん残していきたいなぁと感じましたね。
ーー“リンリン” として、BiSHにおける一人の大切なメンバーとして、それは実現できていたと思うんです。そこについてはいかがですか?

ANDO:BiSHの活動においては、まず、作詞を担当できたのがものすごく大きかったですね。自分がどうってことないと思いつつ書いた言葉たちが、歌詞が、清掃員(ファン)たちにすごく喜んでもらえたり。言葉も、絵と同じく、残っていくものだと思います。そこはうれしかったですし、やりがいがとても大きかったです。
解散前に自分一人で音楽を作ってみよう、と思った時。あの期間は、きっと、短絡的だったのかもしれませんね。「曲を作って、自分で歌詞を書いて、それを歌えるなんて、素晴らしいじゃないか」って。漠然とした「いいな」だったんです。
それから時が経って、アートに出会い、確信できたことがありました。それは、自分が1000%自分で作れる、ということ。たとえば公園の絵を描こうと思った時に、どんな遊具を置くのか、何の木を生やすのか、壁はどんな色なのか、どのような人がいて、時間は何時で……と、全てを誰にも頼ることなく、自分で決められるんです。
ーーうん、うん。

ANDO:自分の全てを詰め込んで伝えることができるのは、唯一、アートだなと思った。正直なことを言うと、アートと出会った瞬間、その一瞬にして「音楽では上手くいかないかもな」と思ってしまったんです。それほどに、アートがいい、と感じた。どうなってもいいから見せたい、作り上げたい。そんな想いを形にできる喜び。そういうものたちを実感して、「見てほしい!」と感じましたね。
ーーもちろん、ご自身の音楽活動を自ら卑下するのでは、なく。それ以上の熱量を「絵」から当てられてしまった。すごく失礼な言葉かもしれないけれど、ひとつ聞いてもいいですか?
ANDO:もちろん。
ーー初期の熱量って、いつまでも続くのかな、と不安に思ってしまったんです。水を差すような形になってしまってはいけないけれど。ANDOさんが抱いたアートへの志は、いつまでも同じ熱さで続くのかな、って。

ANDO:BiSHの時を思い出しました。わたしが作詞を担当した『beautifulさ』という曲があって。『どんなとげとげの道でも 息してれば 明日は来るんだし 泣いた後に咲くその花はso beautiful beautifulさ』と、歌詞を書きました。「今その時」だからこそ書けた歌詞だったと思うんです。あの曲はまさに。

ANDO:「今その時」にしか思えないもの、その熱量は、きっと一生あり続けると思うんですよね。絵に関しては、わたし自身、知らないことばっかりです。現在地点では。ただ、これからさまざまなものに出会って、それらから影響を受けて、きっと、なんだって絵にしていけると思う。日々、たくさんのものから影響を受けている実感があるんです。正直それは、幼稚な視点かもしれないけれど、今のわたしができる精一杯は、今にある。そう思うんです。


ANDO:今回制作した作品だって、そうです。わたしがこれまで体験してきたほとんど全てをまとめて、ひとつのアート作品にした。これは紛れもなく、それぞれの瞬間に存在していた「今」がひとつの作品として、形になったものなんですよ。幼少期に作った図工の作品、幼い頃に買い与えてもらった人生ゲーム、BiSHの衣装だってそう。お母さんがお弁当として塾に持ってきてくれた、アイスクリームが詰まったお弁当箱もそう。あの時々の「今」がつまっているんです。
ーー「今」が、いつまでも続いていく。まさしくキース・ヘリングが言った言葉にも近いですよね。

ANDO:そう思います。BiSHのみんなと居た時、家族以上に、本当、ずーっと一緒に過ごしていたのですが、その時だけは「変なヤツ」として扱われなかったんです。幼き頃にはいつも周りから「変な子」としてみなされていたんだけど、BiSHのメンバーだけは違った。お互いの悪いところも、変なところも、全部含めて「いいね、いいね」って支え合ってきたんです。
ーーうんうん。


ANDO:みんなが「面白いね」と、認めてくれた。「そういう子供らしい視点がすごくいいと思う」と言ってくれた。わたしが今できること、そのとき感じたことを、しっかり受け止めてくれたんです。これからは、わたし自身が、わたしに対して、そうありたいなぁ、って。さまざまなモノやコトを面白がって、どんどん影響を受けて、たくさんの作品を作っていきたい。そう感じています。
ーーありがとうございます。静かに燃える熱い炎のような、そんなインタビューになりました。最後にひとつ、何かメッセージのようなものがあれば、ぜひとも聞かせていただきたいです。

ANDO:では、野望をひとつ(笑)。わたしが憧れたアーティスト、キース・ヘリングは、日本のことが結構好きだったみたいで。過去に何度も日本を訪れていたのだそうですが、その時、青山と表参道の間ぐらいにある壁にペイントをおこなったようなんです。
ーーほう。
ANDO:ペイント自体は、すでに撤去されてしまったようなのですが、その壁の向かい側に『ワタリウム美術館』という場所があって。今は、そこで個展を開催してみたいんです。その近くて遠い夢を、きっとこれから叶えられたらいいなぁと思っています。以上、野望でした(笑)。

【編集後記】
パンクロックだ、と思った。瞬間・刹那の輝きに全ベットし、脇目も振らず、突っ走っていく。“楽器を持たないパンクバンド” のメンバーとして活躍してきた今日までを一度手放し、音楽という武器を置き、新たに “筆” を手にした。一人の “芸術家” として、彼女はきっと、“グレーな日々” をカラフルな色で塗りつぶしながら生きていくのだろう、と。そう思うのだ。
彼女が書いた歌詞を、ここにひとつ置いておこう。

『どんなとげとげの道も、僕らは乗り越えていくんだし 困難裂いて、過去は忘れ、晴れた明日へと行こうぜ』
取材後の空、夜は深く暗かったけれど、確かに星がキラキラと煌めいていたのだ。