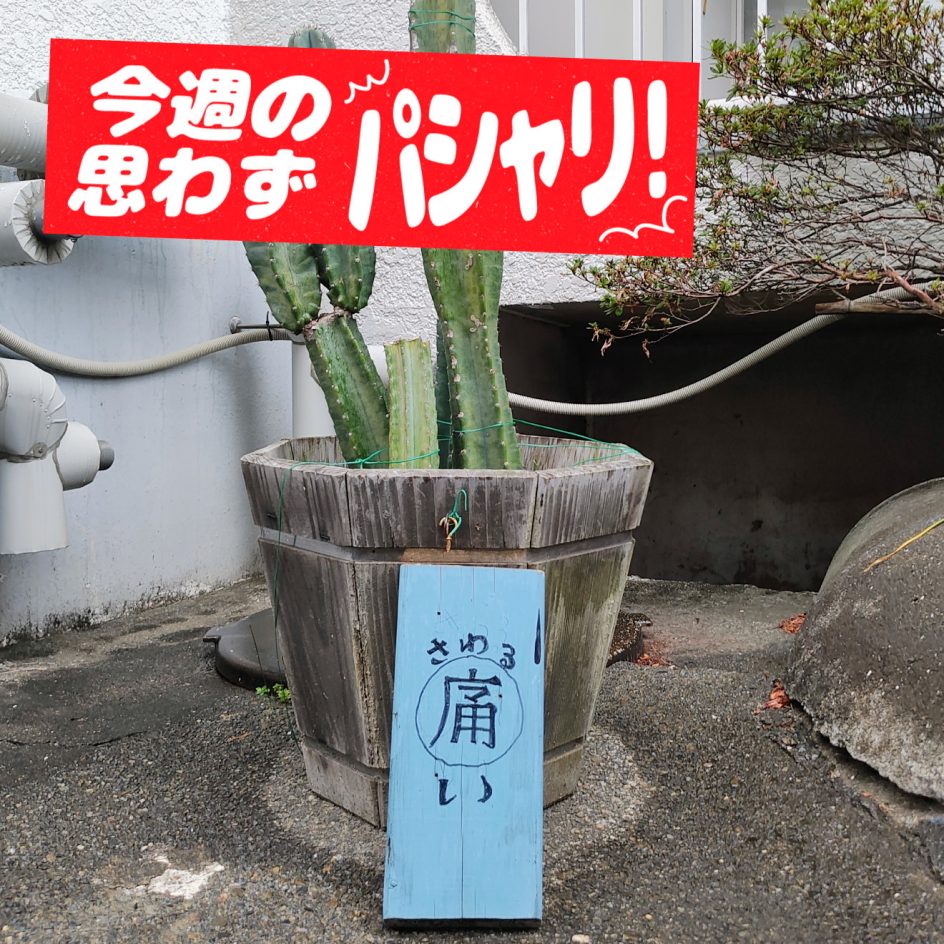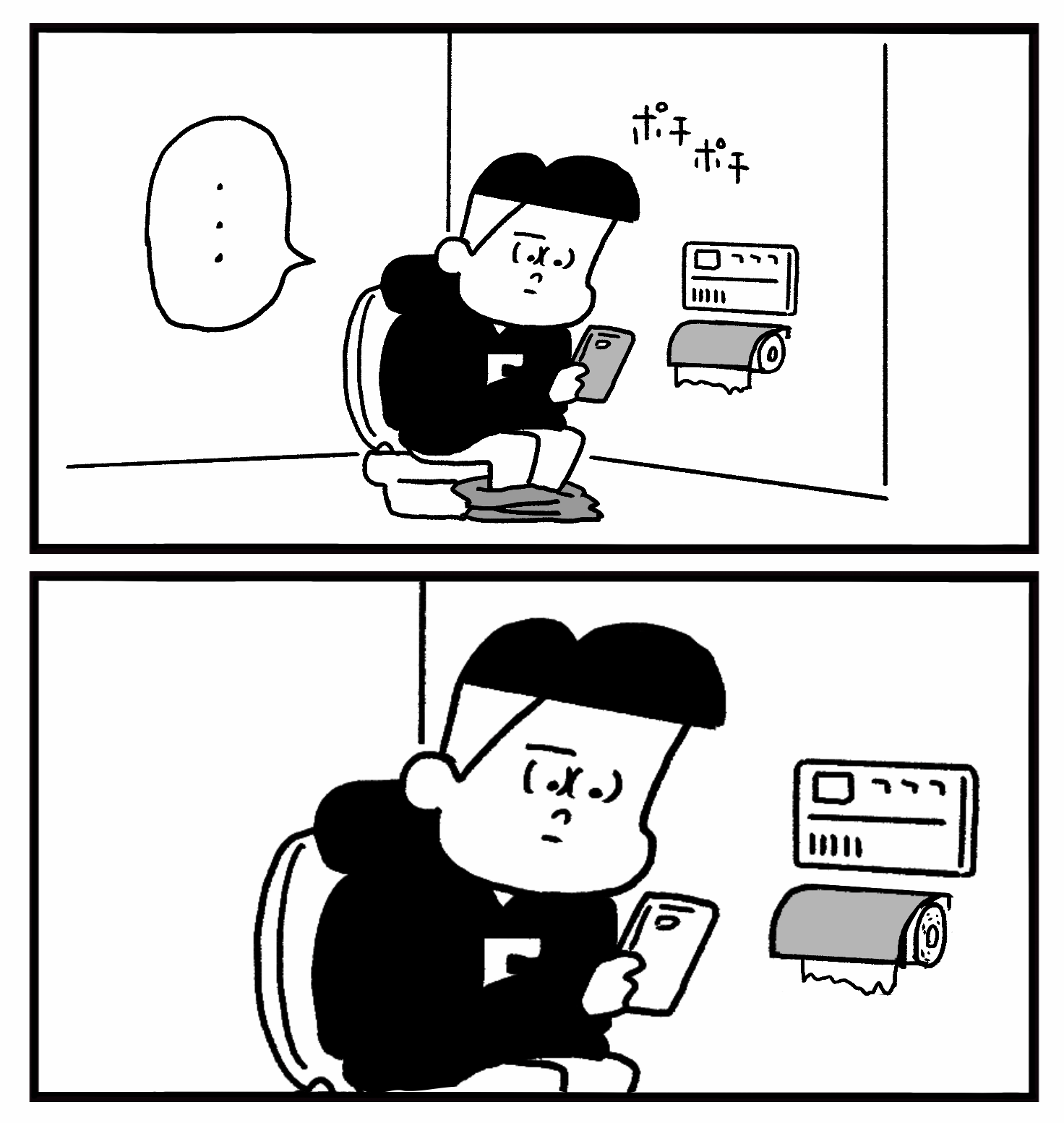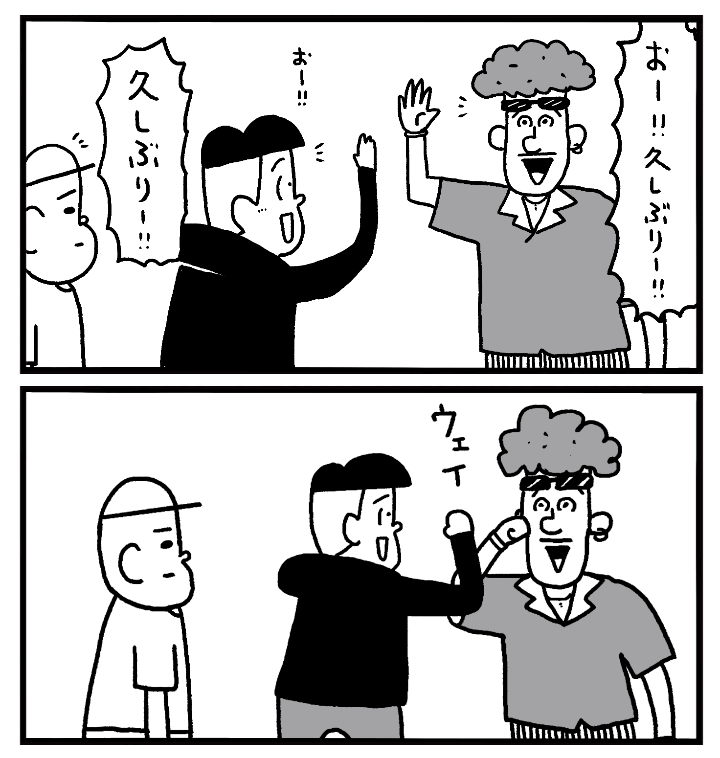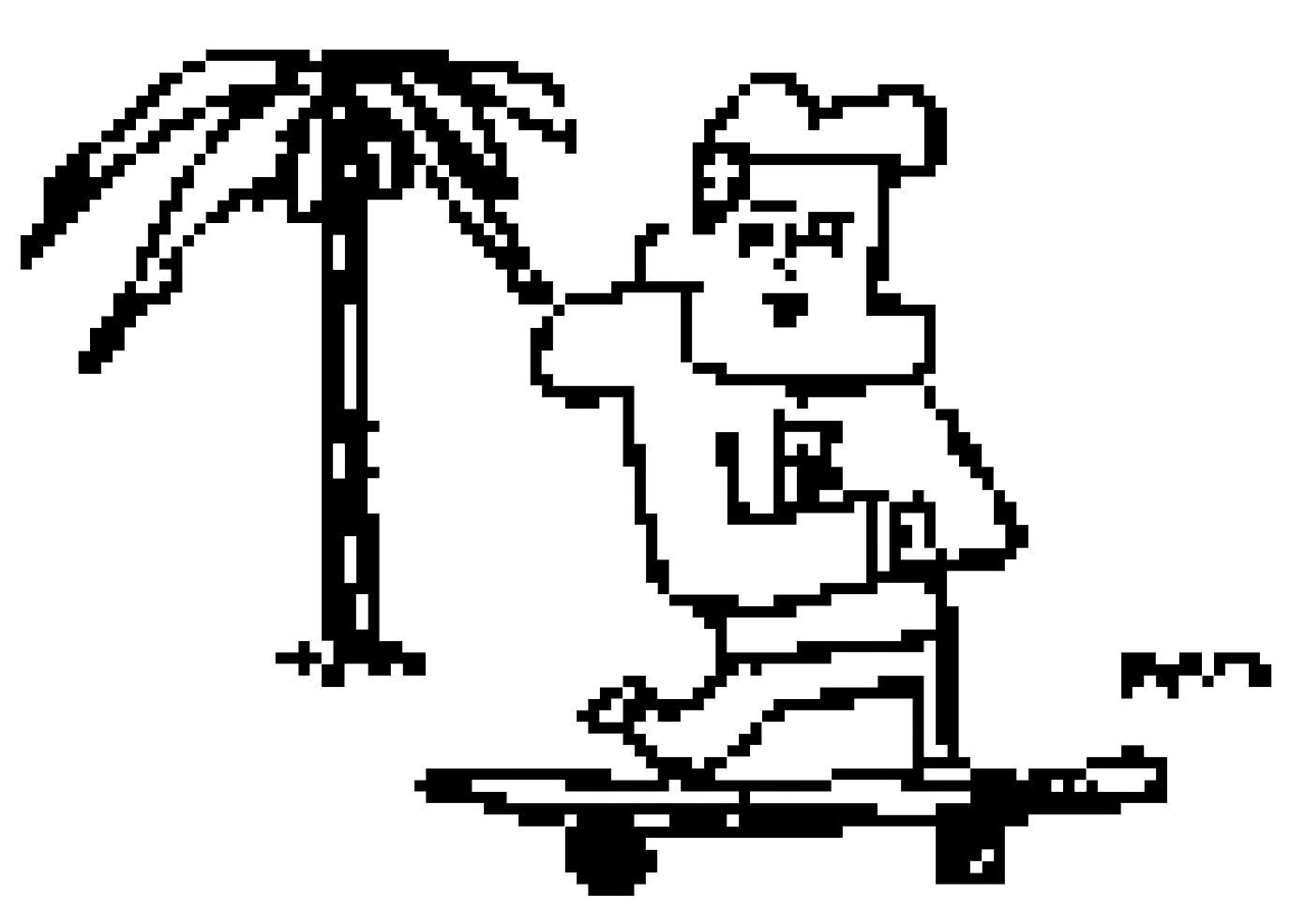サブスクが主流になり、外でも家でも大量のコンテンツを消費できる時代だからこそ、何を観たらいいのか分からない!という人も多いのでは?「シネマフリーク!!」では、映画館で上映中の話題作から、ちょっとニッチなミニシアター作品、おうちで観ることのできる配信作品など数多ある映像作品の中からライターの独断と偏見で、いま観てほしい一本を深掘りします。
ホロコーストや強制労働によりユダヤ人を中心に多くの人びとを死に至らしめたアウシュビッツ強制収容所。今回は、その隣で平和な生活を送る所長一家の日々の営みを描いた『関心領域』をピックアップ。ポスタービジュアルからも伝わる不穏な気配に、終始心がざわつく衝撃作品です。

© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
タイトル:『関心領域』
監督:ジョナサン・グレイザー
出演:クリスティアン・フリーデル、ザンドラ・ヒュラー
配給:ハピネットファントム・スタジオ
2023年製作/105分/アメリカ・イギリス・ポーランド
<あらすじ>
空は青く、誰もが笑顔で、子供たちの楽しげな声が聴こえてくる。そして、窓から見える壁の向こうでは大きな建物から黒い煙があがっている。時は1945年、アウシュビッツ収容所の所長ルドルフ・ヘス(クリスティアン・フリーデル)とその妻ヘートヴィヒ(ザンドラ・ヒュラー)ら家族は、収容所の隣で幸せに暮らしていた。スクリーンに映し出されるのは、どこにでもある穏やかな日常。
しかし、壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音、建物からあがる煙、家族の交わす何気ない会話や視線、そして気配から着実に伝わってくる。壁を隔てたふたつの世界にどんな違いがあるのか?平和に暮らす家族と彼らにはどんな違いがあるのか?そして、あなたと彼らとの違いは?
『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』(2013)で知られるユダヤ系映画監督ジョナサン・グレイザーがイギリスの作家マーティン・エイミスの小説を原案に手がけた本作は、第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門でグランプリ、第96回アカデミー賞で国際長編映画賞と音響賞を受賞した注目作です。
映画監督としてだけでなく、ジャミロクワイの「Virtual Insanity」やレディオヘッドの「Karma Police」など、90年代のロックシーンで活躍した映像作家としても知られているジョナサン・グレイザー。本作でも映画的な感傷を排除し、当時そこにあった光景から私たちの現在地へと普遍的につながる無意識の悪意や作為を浮かび上がらせる実験的な映像演出が随所に散りばめられています。

© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
マーティン・エイミスによる原作本のなかでは、ルドルフのモデルとなった収容所の所長や青年中尉、被収容者でありながら同じユダヤ人たちの遺体を処理する特別労務班の班長など複数の語り手による手記のような形で、そこで起きた日々が淡々と描かれています。
そこでは処刑描写や人を道具として扱う残忍な労働体制について詳細に説明されているのですが、映画ではより俯瞰的に対象を絞り、所長一家の穏やかな生活を中心に鑑賞させる構造になっています。(実際の撮影も屋敷のいたるところに無人カメラを設置して、一家の暮らしを覗きみるような形で行われたそう)
この映画を観ようかどうかどうか迷っている知人たちからは、「怖い?」「観たら落ち込むかな?」という質問が多く寄せられるのですが、これまでに公開されてきた数多くのホロコースト関連の作品と比較して、直接的な暴力や残虐描写はありません。だけれど、歴史を知る自身の想像力と掛け合わせるととてつもなく恐ろしく、観終わったあとは自分自身のなかにも存在する無関心という暴力性について考え、ひどく落ち込んだのが正直な感想です。

© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
夫婦と5人の子供たち、そして子供たちの世話をする家政婦たちが仲睦まじく川べりでピクニックをするシーンから始まり、翌朝には庭で家主であるルドルフの誕生日会が慎ましやかに行われます。
妻であるヘートヴィヒのこだわりが詰まった立派な邸宅と家を取り囲む美しい庭園は、幸せの象徴として描かれますが、有刺鉄線が取り付けられた高い壁の向こうには、約96万人のユダヤ人が処刑されたアウシュビッツ強制収容所が広がっているということを忘れてはいけません。
穏やかな家族の風景。しかし、画面の端には塀の奥から立ち上り続ける黒い煙、家族団欒の背後にも貨物列車の動きに合わせて動く煙がちらつき、耳をそばだてると誰かの怒号や悲鳴、銃声のような騒音が聞こえてきます。
ヘートヴィヒは殺されたユダヤ人女性が身にまとっていた立派な毛皮のコートを誇らしげに試着し、幼い息子たちは夜な夜な殺された被収容者の金歯を数えて眠りにつき、休日に出かける川には遺骨が流れる。楽園のように描かれた一家の暮らしの隣で行われている残酷な現実は彼らの日常にぴったりと寄り添い、たびたび顔を出しますが当の本人たちはその異常性に気づいていないかのように振る舞い続けます。

© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
私たち鑑賞者に警鐘を鳴らすのは、生まれたばかりの末っ子と遠い故郷から遊びにやってきたヘートヴィヒの母親。赤子は昼夜問わず泣き続け、最初は娘の贅沢な暮らしぶりに感心していた母親も常に漂う異臭や騒音に徐々に疲労の色を見せ、しまいには娘に無断で帰ってしまいます。
それでも自身が作り上げたこの環境を守りたいヘートヴィヒは、ルドルフの昇進にともなう転勤の指令が出ても都市部についていくことを断固として拒み、この歪んだユートピアの女王として君臨することを選びます。

© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
家族の物語と並行して作中では、レジスタンス(反独活動家)として暗躍する1人の少女の姿を軍用の暗視カメラとサーモグラフィという特殊な映像が捉えます。この少女のモデルとなったのは実在するポーランド人の女性で、眩しい熱を感じさせるその演出は主人公家族たちの闇と対極をなす光のエネルギーとして彼女が行った過去の行動を映し出しています。
また、物語の終盤では転勤先で淡々と仕事をこなすルドルフが見るひとときの幻影として、現在のアウシュビッツの姿が唐突に現れます。実際に被収容者たちが身につけていた囚人服や押収品が歴史の証人として展示される空間を、当たり前のように慣れた手つきで清掃する2人のスタッフ。こういった異なる価値観や時代性を映像のなかに組み込むことでより一層本編の不快さが際立つように感じました。

© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
2024年はクリストファー・ノーランによる『オッペンハイマー』、そして現在放送中のNHKの朝ドラ「虎に翼」など世界大戦下を舞台にした話題作が国内外で多く公開されていますが、そのほとんどが直接的な凄惨な殺戮や暴虐シーンの再現をあえてダイナミックに映さず、細部を丁寧に描くことで、背後で生きる人々のまやかしの死生観やナショナリズム、心理的な衰弱を巧みに浮かび上がらせることを意図し、制作されています。
アカデミー賞の授賞式でガザで現在起きている問題に言及し、議論を巻き起こしたジョナサン・グレイザーは公式インタビューで、「この映画は偏見、抑圧、国家による支配、非人間的な考え方の恐ろしさを語るものです。それらと同じ衝動はホロコースト後にも存在してきました。現在起こっていることについて誰かと喧嘩するつもりはありません。私が興味を持つのは、平和、理解、仲直りを訴えることです」とコメントしています。私たちが過去の出来事として単純に胸を痛めたり、グロテスクな描写に注目した議論を進めるのではなく、現在進行形の事象として自分自身、そして世界を見つめ直すように訴えかける本作。
まるで今を生きる私たちと同じように残虐さと紙一重の世界で淡々と暮らす主人公たちの姿から、何を見て、何を聞き、何を感じるのか。日々起きていることについて目を背けずに、五感を使って感じ、考えていきたいと思わせてくれる一本です。

© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.