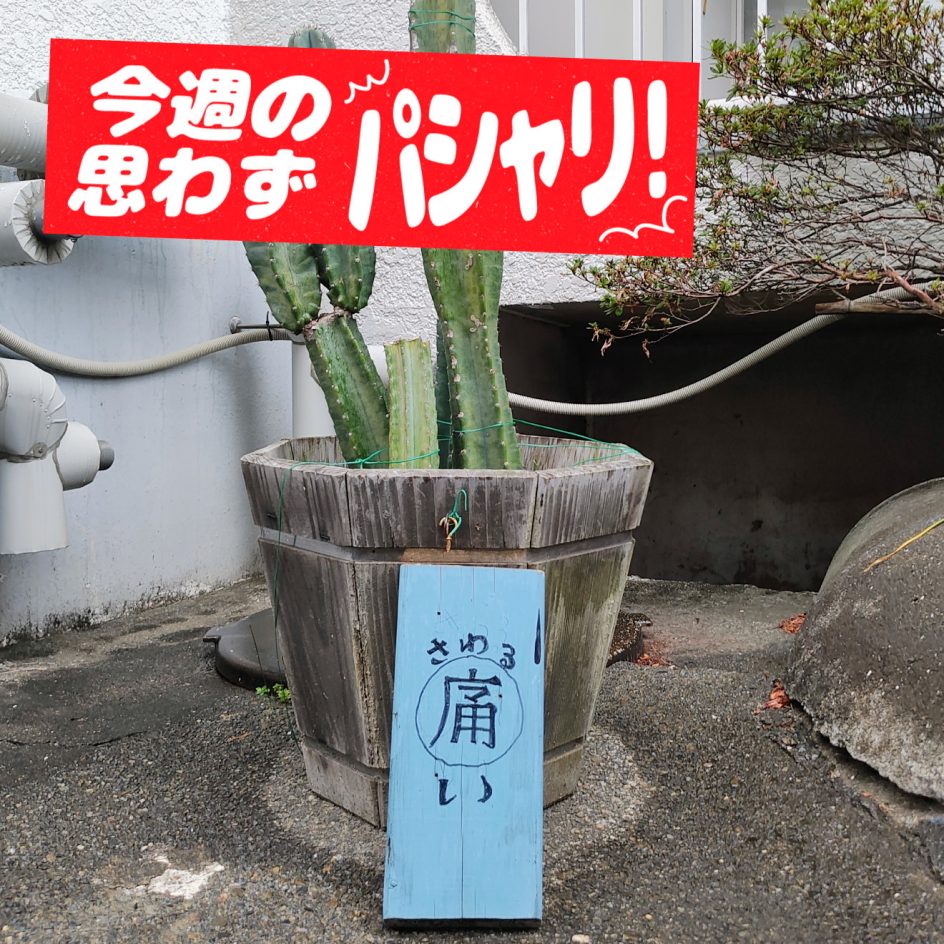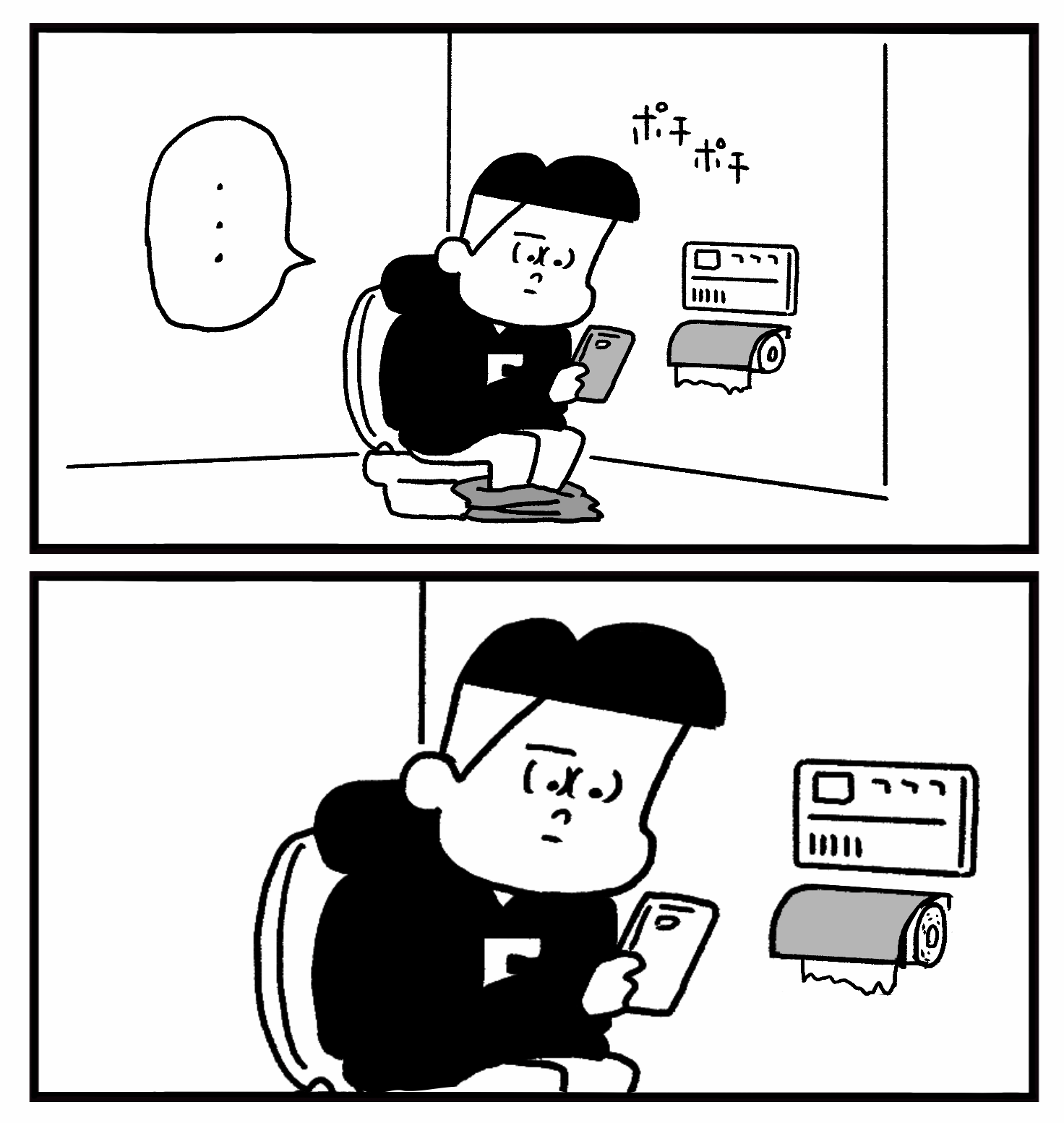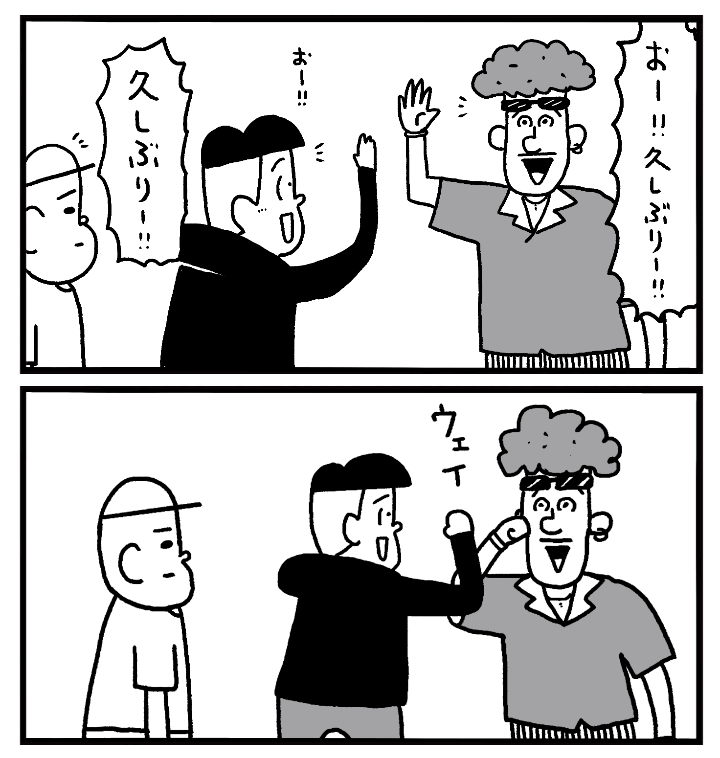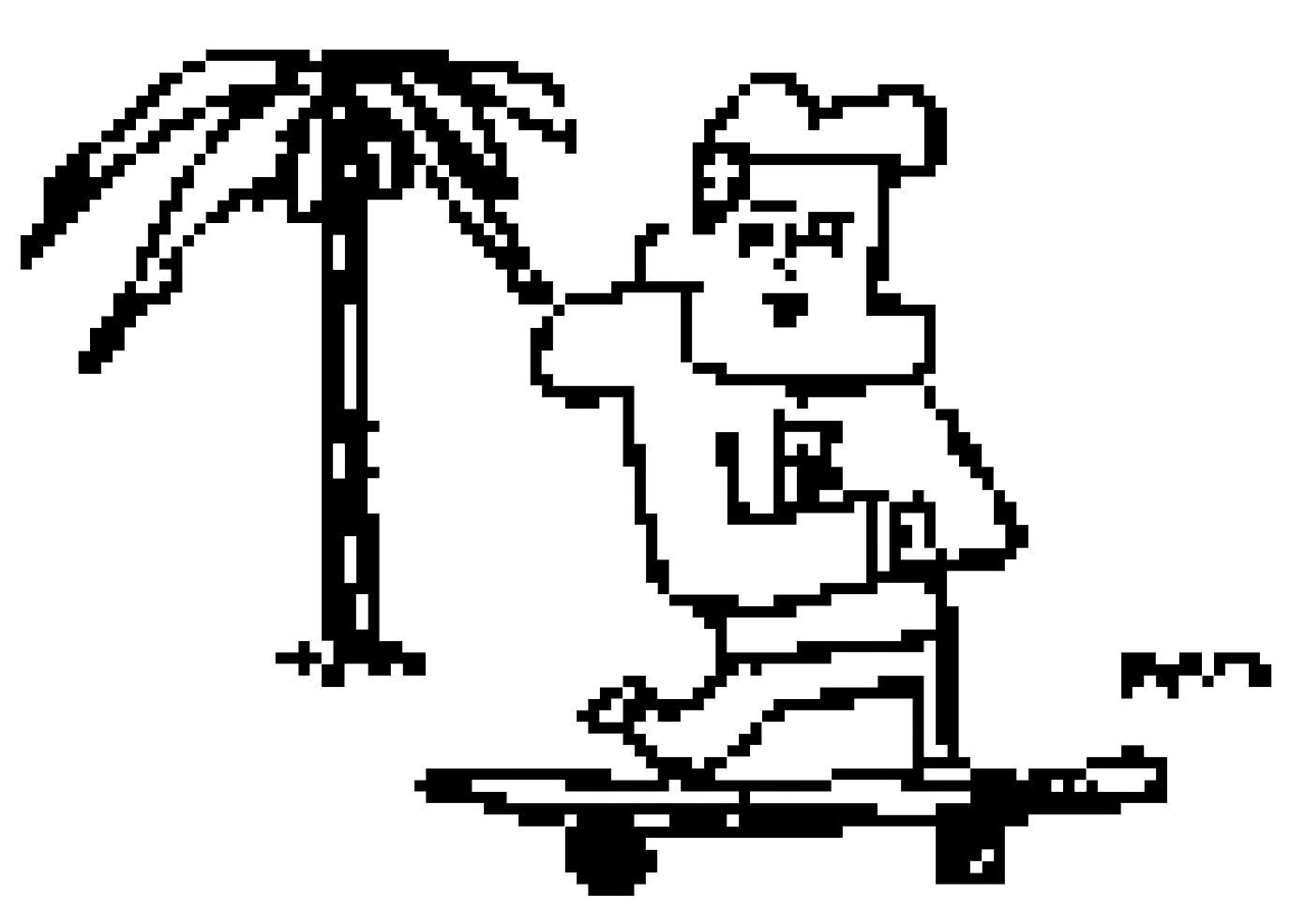それぞれの現代を生きる皆様にお届けする新連載、“となりの「クィア」のリアルボイス”。
ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダさんが本企画のホスト役となり何か新しい気づきとなるようなトークセッションを繰り広げます。第2回目のゲストはクィア当事者であり、2021年に公開された東海林毅監督の短編映画『片袖の魚』でトランスジェンダー女性の役で主演、そしてKASHISH Mumbai Queer Film Festival最優秀主演俳優賞を受賞されたモデル・俳優としてご活躍中のイシヅカユウさんをゲストにお招きしました。
___LGBTQ +当事者として様々な場面で活動しているお二人ですが、対面するのは今日がお初なんですよね?
ドリアン・ロロブリジーダ(以下:ド)「インターネット上ではやり取りさせていただいたことがありますが、お会いするのは初めてですね」
イシヅカユウさん(以下:イ)「そうですね。よろしくお願いします!」

ファッションモデル / 俳優
イシヅカユウ(ISHIZUKAYU)

ドラァグクイーン
ドリアン・ロロブリジーダ(Durian Lollobrigida)
ド「まず大前提として、イシヅカユウさんはセクシュアリティを聞かれた場合にどうお答えしていますか?」
イ「場面によってトランスジェンダーと言うこともありますが、基本的には“(注1) MtFの女性、そして今のところはヘテロセクシャル”。そうお答えしていますね」
ド「なるほど。我々は“セクシュアリティ”というものをフックにお話をさせていただくことが多いじゃない? でも私は常々自身のセクシュアリティを100%意識した状態で生きているかというとそうではなくて。自分の場合ゲイではあるけれど、それ以前にパフォーマーだし、ドラァグクイーン。さらに私の言葉はゲイ代表の言葉ではなく、あくまで私個人の意見や考えでしかない。だから毎回セクシュアリティが枕詞のようについてくることに、なんだかなぁと思うこともあったりするんだけど、ユウさんはどうかしら?」
イ「それは本当にその通り、めちゃくちゃ感じます。例えば俳優やモデルの仕事をする時に、身体的な事やセクシュアリティを意識した表現だけをし続けるわけじゃないじゃないですか。だからそこにモヤッとすることもあります。でも逆にそこから解き放たれているなと思う瞬間もありますね。自由だなって。その上で色々な場所でお話しさせていただく時には、『これはあくまで自分の考えなんですけど』という事は必ず伝えるようにしています。それって本来当たり前の事でもあるとは思うんですけど、ちゃんと念押ししておきたいんですよね」


ド「難しいところですよね。セクシュアリティというフックがあったからこそいただけたお仕事もあるわけだし、そこを完全にゼロベースにしたいかと言われたらそんなことはないんだけれども、毎回それが付いてきてしまうと、実際の仕事の内容が二の次になってしまっているんじゃないかという不安は拭えなくなってしまうわよね」
イ「そうですね。そもそもセクシュアリティは自分の中にある様々な要素の内のひとつでしかないはずなんですけどね」
ド「私の場合は、ドラァグクイーンという肩書自体がセクシュアリティやジェンダーとは切り離せないものだから仕方がないかなという気持ちはありつつ。今ってLGBTQ +という存在が社会の中でようやく認識・可視化されてきたフェーズで、過渡期なんだと思うので、だからこそユウさんのように矢面に立って活動されている方をリスペクトすると共に、大変なことも多いだろうなと感じています」
イ「おっしゃるように、まさに過渡期というのはすごく感じます。それが故に、ここをフワッと進めてしまうと、これから先の時代にもそれを背負わなきゃいけない人たちが出てきてしまうじゃないですか。だから私は、意識的に背負う。そして背負いながらも同時に“これは本当は私だけが背負うものでもない”っていう事も伝えなくてはいけないと思っていて。でもそれを両立するのはすごく難しい」
ド「難しいですよね。そしてやっぱりね、イシヅカユウは戦う女なのよね。 世の中から投げかけられる不条理だったり悪意みたいなものと戦っているのを、SNSなどで目の当たりにしていました」
イ「その節はメッセージで励ましていただいたり、本当にありがとうございました……!」

ド「最近はいかがですか? 世の中の無理解や悪意みたいなものに晒されることはまだある?」
イ「もちろんあるんですけれど、日本においてはSNS上でのことがほとんどなので、それって見ないことも可能だし、見なくってもいいなって思えるようになってきました。いい距離で切り離して考えることができるようになってきたというか。以前はスルーできなかったから返信して戦っていたんですけれど、それってやっぱり疲弊しちゃうんですよね。そういうことって無限に湧いてくるし。最近は名指しで色々書かれているのを見ても『ブロックすればいいじゃん!』って考えるようになりました」
ド「それはよかった!」
イ「やっぱりセーラームーンとかチャーリーズエンジェルとか観て育ってきたので、根本的には戦いたい感じなんですが(笑)」


___戦闘派なんですね! その戦いから一歩線引きできるようになったのには何かきっかけがあったんですか?
イ「なんだろう……。やり切ったって言うと違うんですけれど、ある時ふとそう思えるようになりました。でもそれって一回ちゃんと戦った上で思えたこと。戦った上で、次の段階の考え方をできるようになったのかなと思います」
ド「SNSには様々な言葉が溢れているし、全員に好かれることってまず無理ですよね。どれだけ気を付けていても嫌われる人には嫌われる。でもその分、好いてくれる人や評価してくれる方はいらっしゃるから、好いてくれない人に自分の人生の時間や労力を割くのはもったいないなって私も最近思います。私、八方美人だから昔は『全員に好かれたい』って思っていたんですが、どうせ嫌われる人からは嫌われるから、だったら好いてくれる人とのコミュニケーションを大切にしたいと思うようになりました。時間は有限だし、そのほうが健やかじゃないですか」
イ「わかります。戦っていた時期は、私を応援してくれている人や自分と同じような当事者の方々の為にも頑張ろうと思っていたんですけれど、そのパワーを違った形で使って、好いてくれる人たちに返していこうと思えたことも大きいです」


___一言で括ってしまうと乱暴かもしれませんが、それでもLGBTQ +という言葉やそれに該当する人々への認知は広がる中、お二人から見て世の中や世間からの反応が変化したと感じる事はありますか?
ド「LGBTQ +の人々を総括して語れないということを大前提としつつ、私が思うに、今までは例えばMtFやトランスジェンダーの方って、それこそショービズや夜の世界で職業としての“ニューハーフ”としてでしか世の中から認識されずにいて、可視化されていない人たちはひっそりと息を潜めることを強いられてきたというところがあると思うんです。」
「だからこそ、そこでイシヅカユウさんの残した功績はすごく大きい。それまでは夜の世界でもなく、メインストリームに出てパフォーマンスをするという方を自分はそこまで存じ上げなくて。ようやくこういう方が出てきたんだなって、とても嬉しくてずっと拝見していました。そんなふうに頑張ってくださっている方々がいて、私も自分にできる表現をしている中で、こういった企画にドラァグクイーンをホストに置いてくださるところなども世の中が変わってきている一環かなと思いますね」
イ「ドラァグクイーンだったらドラァグクイーンの場所、トランシジェンダーといえばトランシジェンダーだけ、みたいな感じは大分切り崩されてきている気はしますよね。トランスジェンダーのMtFだけで言うと、私の前にも佐藤かよさんやミュージシャンの中村 中さんがいらっしゃって、ここ20年くらいでそういった方々の功績で変わってきた事は本当に多い。ありがとうございますって気持ちがすごくありますね」
ド「自分はパートナーがトランスジェンダー男性((注2)FtM)なんですが、L・G・Bは自分の身体とジェンダーアイデンティティがある程度合致している方々が多い中で、トランスジェンダーの中には特に色んな自認の方がいらっしゃるのを感じます。例えば私のパートナーは『自認はトランスジェンダー男性』なんですが、『自分は男性』と思っている方もいれば『自分は男性的な女性』と思っている方もいる。そこのグラデーションによって、一枚岩にはなりにくいところがあって難しいと感じています」
イ「そうなんです。それが故に、当事者たちの中でも『どっちが正しいんだ?』みたいな話になっちゃうんですよね。自分自身がどういう立ち位置なのかを決めなくてはいけないというか。本当に全員違うし、それぞれがそのままでいていいはずなのに、現状ではそこが難しく、なぜかバトっちゃうみたいなところがありますよね。そんな不毛な戦い必要ないはずなのに」
ド「本当はユナイトしてもっと大きな“無理解”みたいなものと戦わなきゃいけないのに、自分たちの中だけでそうなっちゃうのはすごく歯痒いところ。我々が相対していかなきゃいけないのはそっちじゃなくてあっちだろ!ってね」
___すべての人がそれぞれ違うとわかっているつもりでも、個性を知り得ない関係性、例えば仕事で会う方や初見の方など、まだ深いコミュニケーションを取れていない段階だと、自分の中にある固定観念から勝手に見た目でジェンダーを決めつけてしまっていたり、“意識していない悪意”みたいなものを生み出していないか不安になることがあります。それってどうすれば回避できるでしょうか?
ド「(注3)マイクロアグレッションの問題ですよね。完全になくす事は難しいとも思います。100人いれば100通りの考え方があるし、私だって自分の中に様々な決めつけや偏見を抱えて生活しているわけなんですが、前提として大切なのは『そういうこと(マイクロアグレッション)をしているかもしれない』と考えることだと思います。一番怖いのは『自分は差別なんかしない!』という人から発せられる小さな偏見や差別。自分を疑う前提さえあれば、自問自答で内省を繰り返して、ちょっとずつ変わっていけるものだと思います。回避するための様々なテクニックもあるにはあるんですが、まずはそういう精神面を振り返ることが大切なのかなと思います」
イ「個人的にできる事はまさにそれだと思います。本当に仲が良い人だと話し合って解決できることもあるかもしれないけれど、例えば職場の親しい人との関係性だったりすると“何でも言っていい関係性”への線引きが難しいですよね。だから、“自分と他人は別の人間”だと思うことをしっかり理解することも大切だと思います。あと社会的なことで言うと、ある程度仕組みでなんとかなるんじゃないかな?とも思います。例えばですけど、企業ってよくアンケートとか取るじゃないですか。あれにそもそも“男・女”の項目は本当に必要かを考えてみるとか。あれのどちらかに丸をつけなきゃいけない状況が辛い人だっているはずだから、そういったことを考えてみる。マイクロアグレッションって直接言われる言葉限定じゃないと思うんです」
___確かにもはや“男・女”だけの項目ではないですよね。そもそもあれって必要なんですかね?
ド「検診や保険だったり、そういう場面で必要とされるのかしら? 技能や技術を測る上では全く必要ないわよね」
イ「必要なことでのアンケートだったらわかるんですけど、結構どんなアンケートにも“男・女”の項目ってないですか?」
ド「忘年会の出し物のアンケートとかね(笑)」
イ「そうそう! この前飲食店に行ったんですけど、最近ってオーダーがタッチパネルじゃないですか? あれに“男○人、女○人”って押さなきゃいけなくなってて……。怒っちゃいました(笑)!」
ド「怒っちゃったんだ(笑)」
イ「会社が決めたことでしょうからその場で店員さんに怒っても仕方ないので、それこそアンケートにしっかり意見を書かせてもらいました!」
ド「マーケティングの考え方が古くアップデートできていないお店だったんでしょうね。特にそういった会社ではカミングアウトもし辛いだろうし、とは言えプライベートのことを全く話さないのもチームビルディングや組織運営的にも難しいし、話したところでマイクロアグレッションに繋がりかねないですよね。そういったところもすごく難しいと思います」
イ「何かを話したときに否定されるんじゃないかって感じることが一番怖いですよね。私も自分がトランスジェンダーだということを相手に伝えた時に『え、それって……』みたいな感じで否定的、嘲笑するような態度を取られることがいまだにあります」

ド「あと、こういう方もいらっしゃいますよね。『私、そういうの全然気にしてないし、認めてるし良いと思う〜』とか。何で良いか悪いかをあなたにジャッジされなきゃいけないんだよ的な。マジョリティ=ジャッジしても良い立場にいるという考え方を知らず知らずのうちに持ってしまっているのかもしれない」
イ「わかります! お互いをジャッジするんじゃなくて、まずは尊重するのが大切ですよね。否定的な言葉を投げかけるべきじゃないし、当事者が話しやすい環境があるだけで全然違ってくるのかなと思います」
ド「そういった環境を作るためには、“人は皆全員違う”というベースをしっかり持っておくべきですよね。みんな何かしらのマイノリティ性は持っているはずなので、企業や組織側もその辺を考えていかないと。本当に今、過渡期だと思うんですよ。戦前~戦後の右にならえ時代から高度経済成長期を経て、その限界を色んな企業や社会全体が感じていて、そこで“戦略としての多様性”の重要性を感じているはずなんです。同じような人間ばかりが集まっていても企業って硬直化しちゃうって気付いているはず。でも本当に大切なのは、戦略としてではなく“それが正しいことだから”っていう事は忘れないでいただきたい」
イ「企業がそういった取り組みを大々的にする事は、もしかしたら(注4)クィアベイティングだと言われてしまうことがあるかもしれないけど、だとしても発信していないと当事者に届かないと思うんです。そこに当事者たちが居やすいかどうかは小さな事で全然変わってくる。わかりやすくレインボーフラッグが置いてあるとか、企業の方のパソコンにステッカーが貼ってあるとか、そうゆう目に見えるちょっとしたことでも当事者は安心できると思うんです。もちろんそれと並行して社員がマイクロアグレッションについて学ぶ場も必要ですけどね」
ド「ポーズだけだったとしても、まずはアクションをしていただかないと、学んでいけないですもんね。もちろんあまりにも実情が伴っていないと批判を受けたりもするだろうから、絶対に両輪が必要。「実はこっそり研修してたんですー」と言われても、こっちは知りようがないから。この会社には味方がいるんだよっていう事を知れる事が大切ですよね。レインボーフラッグや(注5)アライ (LGBTQ +への同調者や支持者)の存在、レインボーバッジやステッカーにどういった意味があるか、それをどこまで理解しているのかを発信する前に、まずはそういった人たちが組織の中にいる会社なんだよと知るだけで、当事者がホッとできる事は多いはず」

(注1) MtFとは、「Male to Female」の略で、生まれたときに男性という性を割り当てられたものの、女性として生きることを望む人を指す。
また、ヘテロセクシャル・ヘテロセクシュアリティとは、性別またはジェンダーが異なる人同士、男性と女性の間での親愛や性愛を指す。
(注2)FtMとは、生まれたときに女性としての性を割り当てられたものの、男性として生きることを望むトランスジェンダーの方を指します。
(注3)マイクロアグレッションとは、無意識の偏見や思い込みが言葉や態度に現れ、否定的なメッセージとなって伝わり意図せず誰かを傷つけてしまうこと。
(注4)クィアベイティングとは、実際にセクシュアル・マイノリティではないのに、性的指向の曖昧さをほのめかし、世間の注目を集める手法である。
(注5)アライとは、 「同盟、味方、理解者、支援者、仲間」を意味する英語「ally」から来ている言葉で、LGBTQ+のことを理解し、課題を共に考え、行動する人のこと。
PROFILE
-
-
イシヅカユウ(ISHIZUKAYU)
ファッションモデル・俳優として、ファッションショー、スチール、ムービー等、さまざまな分野で個性的な顔立ちと身のこなしを武器に活動する。出演した映画『片袖の魚』(2021年公開)では、インドのKASHISHムンバイ国際クィア映画祭で主演俳優賞を受賞。