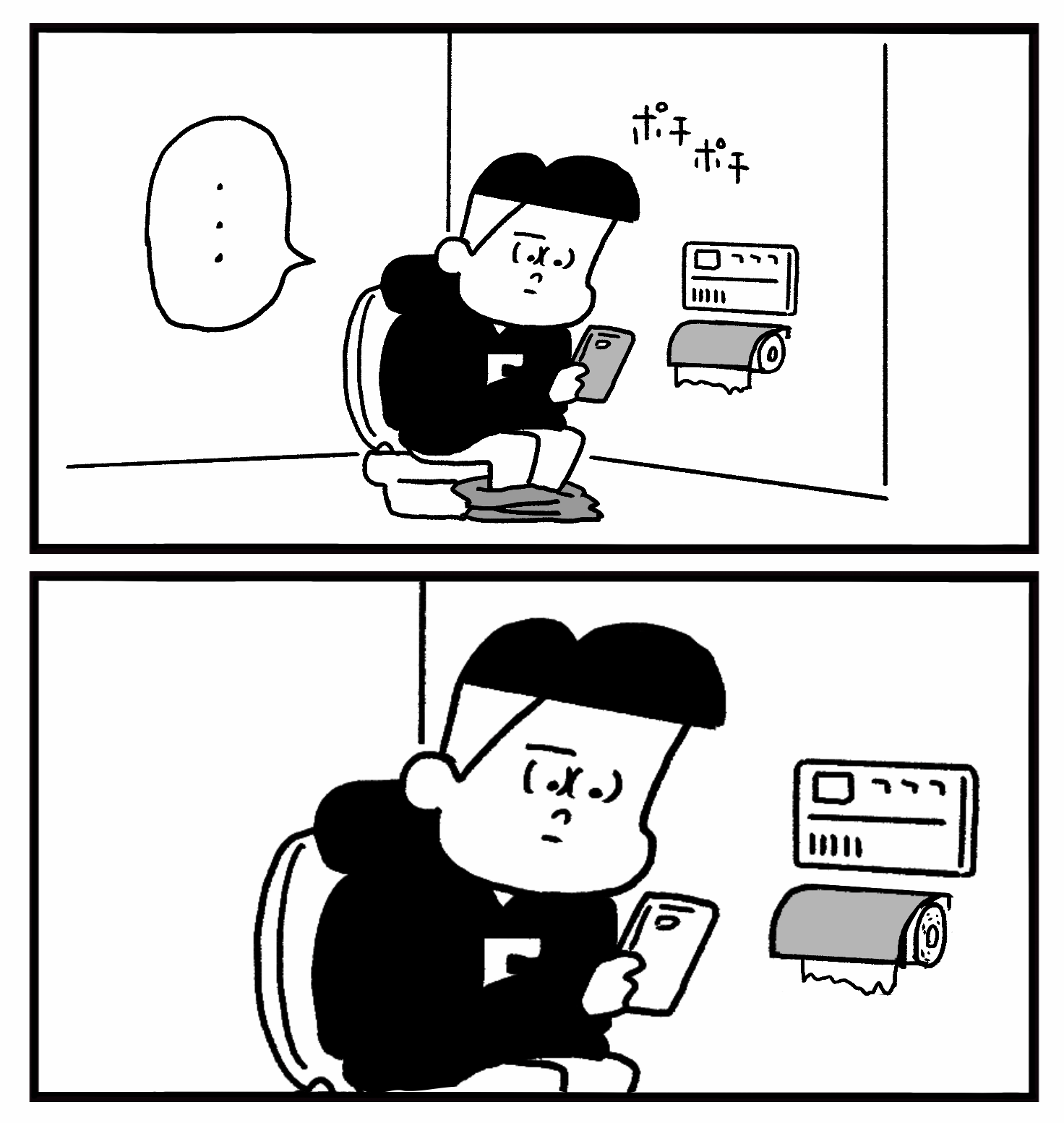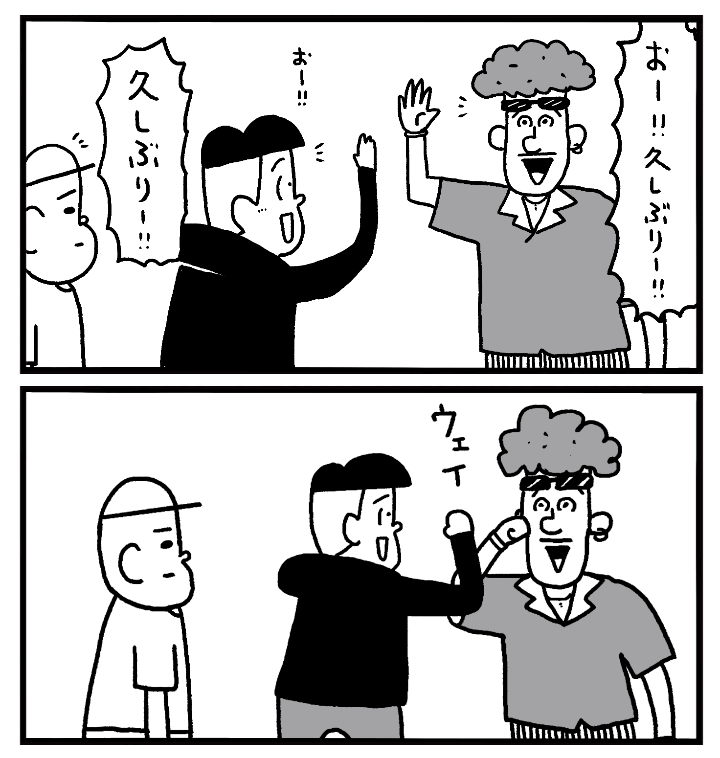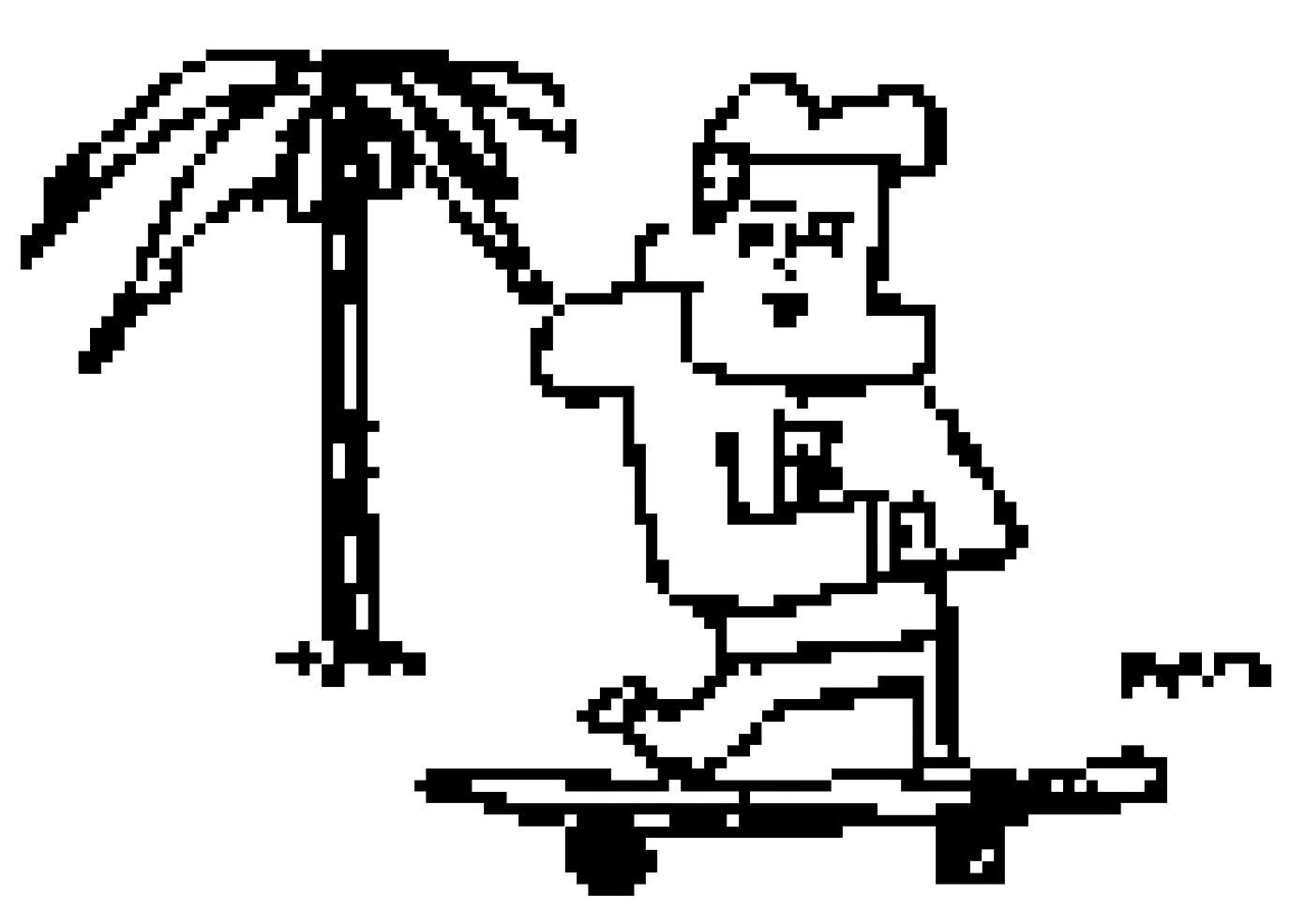サブスクが主流になり、外でも家でも大量のコンテンツを消費できる時代だからこそ、何を観たらいいのか分からない!という人も多いのでは?「シネマフリーク!!」では、映画館で上映中の話題作から、ちょっとニッチなミニシアター作品、おうちで観ることのできる配信作品など数多ある映像作品の中からライターの独断と偏見で、いま観てほしい一本を深掘りします。
衝撃的なタイトルで話題を集める、今年大注目の映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』。今日の社会情勢の延長線上に位置付けられるリアルな世界観、戦闘シーン、そして世界に向けて警鐘を鳴らし続けるジャーナリストたちの生き様に迫った渾身の一本です。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
タイトル:『シビル・ウォー アメリカ最後の日』
監督:アレックス・ガーランド
出演:キルステン・ダンスト、ワグネル・モウラ、スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン、ケイリー・スピーニー
配給:ハピネットファントム・スタジオ
2024年製作/109分/アメリカ・イギリス
<あらすじ>
連邦政府から19もの州が離脱したアメリカ。テキサスとカリフォルニアの同盟からなる“西部勢力”と政府軍の間で内戦が勃発し、各地で激しい武力衝突が繰り広げられていた。「国民の皆さん、我々は歴史的勝利に近づいている——」。就任 “3期目”に突入した権威主義的な大統領はテレビ演説で力強く訴えるが、ワシントンD.C.の陥落は目前に迫っていた。
ニューヨークに滞在していた4人のジャーナリストは、14ヶ月一度も取材を受けていないという大統領に単独インタビューを行うため、ホワイトハウスへと向かう。だが戦場と化した旅路を行く中で、内戦の恐怖と狂気に呑み込まれていくー
A24が史上最大の製作費を注ぎ込んだアクション大作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』。本国・アメリカでは1861年に南北戦争が勃発した4月12日に合わせて公開され、二週連続で全米一位を獲得した話題作です。
IMAXやDolby Cinema®︎といった環境での鑑賞を推奨するほど、映像や音の迫力が圧倒的な本作。私はIMAX環境での試写に参加したのですが、奇しくもトランプ大統領が狙われた襲撃事件の翌日でした。ありえないと思っていたシナリオが今にも起こるかもしれない緊張感あるニュースが続くなか、まるで内戦状態のアメリカに実際に放り込まれたかのような感覚になり、正直この作品をエンタメとしてどのように扱ったら良いのか悩みました。
ただ、「迫力があった」、「面白い」といった一過性の感想では終わらせたくなかったので、今回はいつもよりちょっと真面目に書いてみようと思います。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
監督は『エクス・マキナ』(2014)や『MEN 同じ顔の男たち』(2022)で知られる、英国出身のアレックス・ガーランド。キルステン・ダンストやケイリー・スピーニーといったソフィア・コッポラ監督のミューズとしても知られる俳優陣(実際に、ソフィア・コッポラにケイリー・スピーニーを紹介したのは、本作で共演後のキルステン・ダンストだったそう)が、メインキャラクターである勇敢な戦場カメラマン・リー、そしてそんな彼女に憧れる若手カメラマン・ジェシーを演じています。
コロナ禍のパンデミックの最中で構想が練られたという本作においてアレックス・ガーランドが出発点として考えたのは、多くの問題を抱えながらもドナルド・トランプのような人物が大統領として選出されるのはなぜなのか?そのことにはどんな意味があるのかということ。さらに、これまで矮小化されてきたジャーナリズムの本質や意義に立ち返って、命をかけて戦地から物語を持ち帰り、世界に向けて警鐘を鳴らし続けるジャーナリストというヒーローたちの物語を撮りたかったと語っています。

映画の冒頭で出てくるのは、白髪混じりで顔の四角い恰幅のいい白人の中年男性。演説シーンで語る「我々は歴史的勝利に近づいている—」というセリフすら、「 Make America Great Again(アメリカを再び偉大にする)」というキャッチコピーで政界に進出したトランプ元大統領を彷彿とさせます。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
作中では、時代設定や内戦の原因については明かされませんが、憲法を改正して就任期間を延長、FBIを解体するなど、大統領が独裁的な権力を振るう未曾有の状況下で、一般的には政治思想が対照的とされるテキサス州とカリフォルニア州が政府に対抗して蜂起した近未来が舞台になっています。
フィクションを描くためとも捉えられる設定ですが、歯車の狂った社会においてファシズムに対抗するために保守とリベラルが手を組むことは容易に想像ができるはずだというアレックス・ガーランドのコメントは、非常に辛辣で的を得ていると思いました。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
映画の大筋は崩壊直前のホワイトハウスで、大統領への単独取材を行うために危険を覚悟でニューヨークからワシントンD.C.まで車で向かうロードムービーです。荒廃したフリーウェイを進み、最初の給油スポットでは、略奪を働いた隣人を執拗に拷問する住民と遭遇します。数ヶ月前までそこに存在していたであろう平穏は姿を消し、非情さを隠さない男性に恐怖を感じ、狼狽するジェシー。その異常な光景を無表情で写真に収めるベテラン戦場カメラマンのリー。
その後も一行は、廃墟での銃撃戦や時代に取り残されたかのような観光施設の残骸で撃ち合う戦闘員などさまざまな状況に直面します。一気に緊張感が高まったかと思えば、陽気なオールドスタイルのアメリカ音楽が鳴り響き、束の間の日常を照らし出す緩急ある演出に引き込まれます。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
なかでも一番衝撃的だったのは、ジェシー・プレモンス演じる謎の過激派戦闘員の存在。予告動画でも切り取られている「どんなアメリカ人だ?」という尋問は、世界中で今も広がり続ける分断、そしてそこから派生した人種差別を容易に想像させ、肌の色や国籍を飛び越えて、思想によっても人々を隔て、死へと扇動する恐怖を感じます。
正義のない問いかけ、そしてその迷いのない狂気はどのようにして生まれてしまうのか。殺伐とした展開に戦慄しながら、観終わってからもしばらく考えさせられるワンシーンでした。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
緊迫したロードトリップのなかで語られるのは、「質問はせず、記録に徹する」というジャーナリストとしてのあるべき姿。史上最年少で国際的な写真家のグループ、マグナムの会員になり、世界各国の紛争や内戦の現場を中立の立場で写真に収めることで戦争の無意味さを自国に訴えかけてきたリーは、常にファインダー越しに悲劇を直視し、一線を超えないよう自制しています。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
役作りの参考としてキャストたちが一緒に観たというのが、劇中でも名前が挙がるジャーナリスト、メリー・コルヴィンのドキュメンタリー『メリー・コルヴィンの瞳』(2018)だそう。これはレバノン内戦や湾岸戦争などを取材し、紛争に巻き込まれた人々の姿を世界に伝え続けたメリー・コルヴィンの、最期の現場となったシリアでの姿を実際の映像と再現を交えて描いた作品です。
失われゆく命を目の前にして介入のできないジャーナリストという仕事は、無力さや虚無感、心が麻痺する感覚など想像を絶するような精神状態が常に取り巻いているのだと考えさせられる一方で、ジャーナリズムが抑止力になることを願い、全てを犠牲にして活動を続けたメリー・コルヴィンの姿は、本作でフィーチャーされる真のジャーナリストたちの実像をよりくっきりと認識するのに役立ちました。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
一行はついにワシントンD.C.に到着。かつての首都の姿は跡形もなく戦禍となった状況に、これまで自身が行ってきた報道の意義を見失い、心が壊れていくリーの姿は印象的です。
反対に数々の修羅場を潜り抜け、自分自身のシャッターに存在意義を見出して無鉄砲さを増していくジェシー。一瞬の迷いが命取りとなる前線で、強靭な精神と集中力が二人の間で受け継がれてゆくシークエンスは本作最大の見せ場となっています。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
真のジャーナリズムが不当な扱いを受けて力を失い、世界の大手メディアがプロパガンダの役割を担わされている今。果たしてこの作品のエンディングはどういう未来を暗示しているのか。抽象的な背景にもかかわらず、どんな戦争映画よりもリアルさにこだわった本作が伝えたいメッセージはなんだったのでしょうか。
来月5日には、アメリカ大統領選挙が行われます。その行方は現在、世界中で起こっている戦争や虐殺にも大きな影響を与えるものになるはずで、もしかしたらこの映画のなかの悲劇が実際にアメリカでも起こるかもしれません。そして、日本でも衆議院議員総選挙の期日前投票が昨日から始まりました。少し前まで考えられなかったような、外交上の問題が飛び交う日常を生きている私たちも当事者であると言えるでしょう。
過剰なまでの没入体験を促すこの映画から、起こりうる地獄のような近い未来を想像して、一人ひとりが自分には何ができるのかを考え、語り合うこと。それがアレックス・ガーランドの狙いなのだとこの文章を書きながら改めて考えさせられました。

©︎2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
INFORMATION